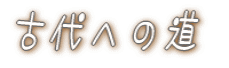
���\�A�����J
�T�v
�@���\�A�����J�Ƃ́A�l�Êw�A�����l�ފw�A�����w�A�n���w���̊Ԃŋ��ʂ��������̈�T�O�ł���B���͈̔͂́A�k�̓��L�V�R��������쓌�ւƐi�݃z���W�����X�A�G���E�T���o�h���̐����܂ōL����B���̒n�ł́A�I���O��萔�����̕����A���������܂ꂽ�B�����̕����̒S����́A��X�Ɠ��������S���C�h�ł���B�ނ́A�X�͊��̂��뗤�����ƂȂ����x�[�����O�C����n���Ă����Ƃ����Ă���i���݁A����̕ʃ��[�g����N����Ă���j�B
�@�ނ炪���������Ă�悤�ɂȂ����傫�ȗv���́A��H�ł���g�E�����R�V�̊J���ł������B�g�E�����R�V�̌���e�I�V���e����葽���̎�������悤�ɉ��ǂ��Ă������Ƃ�����BB.C1�T00�N���܂łɂ͓y������삳���悤�ɂȂ�A�����ւƔ��B���鏀���������������B
�@��ÓT���iB.C�P�W�O�O�`A.D�Q�T�O�j�ɂ����ẮA���L�V�R�p�ݒn��̃I�����J�����A�I�A�n�J�~�n�̃T�|�e�J�����Ȃǂ��������B���J�^�������̃}���n��ɂ����ẮA��ÓT������iB.C�R�O�O�`B.C�Q�T�O�j�ɃG���E�~���h�[���ȂǂŐ_�a�Ȃǂ̋��匚�z���Ƃ��Ȃ��������Z���^�[���a�����n�߂�B���傤�ǂ��̍��A���L�V�R�������n�ɂ����ăe�I�e�B���J���̌��z�������J�n�����B
�@�ÓT���iA.D�Q�T�O�`�X�O�O�j�ɓ���ƁA���J�^������������n�ƃ��L�V�R���������ɂ����Ċ����ȓ�����������悤�ɂȂ�B�y�e���n���̃e�B�J���i���^���j�ł́A�蕶�̏����ꂽ�Δ�̌������n�܂�A���j���オ�n�܂邱�ƂƂȂ�B������L�V�R���������ł́A��̃e�I�e�B���J���ɂ����āA��s���~�b�h�Q�̊������݂āA���̂���Ő������}���Ă����Ǝv����B�i�k������̈ږ����i�g���e�J�l�j��̐N�������������B�j�������A�ÓT������iA.D�U�O�O�`�X�O�O�j�ɂȂ�ƁA�e�I�e�B���J���Ő����̍��Ղ����܂茩���Ȃ��Ȃ�B������}��������n�ł́A�e�B�J���̂ق��Ƀp�����P�A�J���N�����A�R�p���Ȃǂ̑�Z���^�[���u�����n�߁A�e�n�ɒ����Z���^�[��������悤�ɂȂ����B���������̔ɉh�̗��ŁA�푈�������s�Ȃ��Ă����B��������������A800�N���߂��鍠�ɂȂ�ƁA�蕶�̌��������X�ɍs�Ȃ��Ȃ��Ȃ�A���X�ƃZ���^�[�͕���̈�r��H���Ă����B
�@�����Č�ÓT���iA.D�X�O�O�`�P�T�Q�P�j�A���̕���̓}���k����n�Ɉڂ邱�ƂƂȂ�B���̒��S�n�ƂȂ����̂́A�`�`�F���E�C�c�@�B�g���e�J�����̉e�������������s�s�ł���B���̌�A���S�n�̓}���p���Ɉړ]���邪�A��������ɂ���ĂP�S�S�P�N�Ƀ}�������ƌ�������͎̂p�������B����Ń��L�V�R���������ł́A�k�����瑽���̖������ړ������L�V�R���������ɋ����\����悤�ɂȂ��Ă����B���̖����̂����ł��x���ɓ����Ă����A�X�e�J�l�i���V�[�J�j���A����̐��͂̋������������̗b���Ƃ��ď��X�ɗ͂�~���Ă����A���ɂ̓��L�V�R����������т��蒆�Ɏ��߂�悤�ɂȂ����B����͒鍑�ƌĂ�邮�炢�傫���Ȃ��Ă����A���̑��݂͎��͂̑������ɂƂ��ċ��|�ƂȂ��Ă����B
�@�����Ď���1521�N�B�R���e�X�̗�����X�y�C���R�̐N�U�ɂ���āA���̃A�X�e�J�鍑�͊��S�ɔj�ꂽ�B�Ȍ�A���\�A�����J�n��̓X�y�C���ɂ��A������ƂȂ�B������1697�N�܂Ń}���l�i�C�c�@���j�̒�R�͑������B
�L�[���[�h
- �����S���C�h
- �g�E�����R�V
- ����
- ��
- �V���w
- �_�a�s���~�b�h
- �s�s�i�Z���^�[�j
- �푈
��ȎQ�l����
- Michael E. Smith $ Marilyn A. Masson 2000 "The Ancient CIvilizations of Mesoamerica"
- Simon Martin $ Nikolai Grube 2000 "Chronicle of The Maya Kings and Queens"
- �R�a�v�@������ 1997 "���E�̍l�Êw�A�@���\�A�����J�̍l�Êw"
- �֗Y��@�R�a�v 2005 "��g�@�A�����J�嗤�Ñ㕶�����T"

